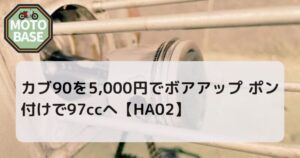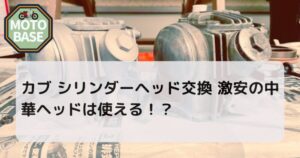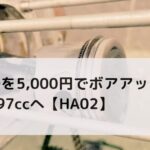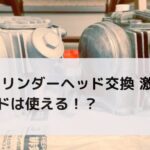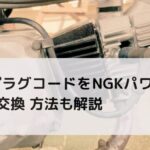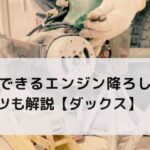カブ ポート加工とシリンダーヘッドOHが効果絶大すぎた!【モンキー・ダックス・シャリー】

前回の記事で「シリンダー&ピストン交換」をしたついでに、シリンダーヘッドもキレイにしちゃおう!ということでOH(オーバーホール)しました。
とはいえ、交換した部品はステムシールだけ…本当の目的は、そう!ポート加工だったんです!(; ・`д・´)
シリンダーヘッド分解

ポート加工とステムシール交換のために、まずはヘッドをバラしていきます。
バルブスプリングコンプレッサーを使ってスプリングを外していくんですが、カムシャフトはすでに取り外し済み。タペットがフリーなら手で外せますが、ベアリング外周が固着している場合などは、カムの出口を下にしてプラハンで軽くトントンしてください。
カムが落ちても傷がつかないようにタオルの上などで作業してくださいね。
※ヘッドによってはタペットを外さないとカムが外れない場合もあります。
・スプリングを縮めるとバルブコッタ(半月型の小さい部品×2)が外れるので無くさないように注意してください。固着していると、いきなり外れてコッタが飛ぶ場合があるので手でガードしながら作業するのがおすすめ!
・外したスプリング、コッタ、タペットなどの部品はIN側とEX側に分けて新聞紙などに包んで分かるようにしておきましょう。
・新聞紙にはIN/EXのメモを忘れずに!
・IN側とEX側を逆につけたり、バラバラに付けたりするとタペット調整がいつまでも終わりません。
ポート加工開始!
いよいよメインディッシュのポート加工です!
初めてなので「これ、やっちゃっていいのかな…?」とソワソワしながら作業しました。
でもこういう作業は思い切りが大事です。(持論)
もし、失敗しても安く手に入りますので!
加工前のポート径は?
キャブからヘッドまで同じ径が続き、バルブ手前でキュッと絞られているのが理想という事なのですが、加工前のポート径を計ってみると
吸気側


- IN(キャブ側):18㎜
- OUT(バルブ側):20㎜
排気側


- IN(バルブ側):17.5㎜
- OUT(マフラー側):19.8㎜
測ってみると理想とは真逆!これはいただけませんね~(`・ω・´)
この状態では一番流速を上げたいはずのバルブ付近の方が広いため流速が落ちてしまいます。
ポートをどのくらい削る?
削りすぎも良くないですし、ちょっと削ったところで意味が無いと思い、とにかく混合気がスムーズに排気まで流れることをイメージして加工後の径を決めました。
という事で、構想はこうだ!
- 吸気側: IN(キャブ側)22㎜ → OUT(バルブ側)20㎜
- 排気側: IN(バルブ側)17.5㎜ → OUT(マフラー側)20㎜
※オレンジが変更点
吸気側はキャブ(PC20)のヘッド側が22㎜なので、段差がなくなることをイメージして、同じく22mmに変更
排気側は削りすぎるとトルクが無くなると聞いていたので、慣らす程度に留めました。
排気側もマフラー径に合わせた大きさにした
これなら、燃焼室内への流入時に流速が上がって流入量も多くなるはず!
という事で、初ポート加工へ
加工方法
削りは超硬バーを使いリューターでゴリゴリっと!やるだけです。
筆者は短い超硬バーで作業しましたが、やり難かったので長めをおすすめします!



こんな具合に削りました。
削った後に測るのを忘れてしまいましたが、入り口をステップドリルの22㎜で削ったので入り口は間違いなく22㎜のはずです。
作業時間は2~3時間ぐらいだったと思います。
集中しすぎて一瞬でした。
ちなみに、ステップドリルの先端は、そのままだとバルブガイドなどに当たって余計なところに傷が入ってしまうので画像のように加工しました。

ノギスで測りながら、ちょっとずつ調整しましょう。
バルブの研磨・鏡面加工


取り出したバルブです。せっかく外したのですからきれいにしちゃいましょう。
バルブの燃焼室側は段差ができるほどカーボンが付着してますね。
対して外側はそれほど付着もなくきれいな状態でした。
バルブの形状加工&鏡面加工
写真は取り忘れてしまいましたが、バルブが閉じている時にバルブの外周部分の厚みでバルブシートとの段差が抵抗になりそうで気にいりません。
あるサイトではその段差(燃焼室側)を斜めにカットしてバルブが開いた瞬間の流速を高めることが出来るそうな。
という事で、こうなりました。


バルブの研磨自体は、グラインダーにバルブを取り付け、回転させながらリューター(超硬バー)とヤスリ、砥石で削りました。最後は青棒で鏡面にしています。

効果があるのか分かりません!(笑)
というか、そもそもボアアップとポート加工も同時に行っていますから検証できません。完全なる自己満足です。
ただ、バルブの鏡面加工について調べてみると効果がありそうな記述を発見しました。
興味が無い方は飛ばしてください。
バルブ鏡面加工(燃焼室側)の効果について
興味がある方は覗いてみてください。

まず「鏡面加工を施すことでの効果」ですが「耐ノック性の向上」とのこと。つまりノッキングをさせないようにする技術です。
ノッキングとは、不適切なタイミングで混合気に自然着火してしまう現象のこと
通常はタイミングベルトやチェーンによってバルブ開閉や点火タイミングがキッチリ決定されているが、別の要因、例えばピストンでの空気圧縮時に発生する温度上昇などにより不適切なタイミングで自然着火してしまう現象です。これは、圧縮比が高くなるほど発生しやすくなるため、圧縮比の高いエンジン(ターボ等)はハイオクを入れる必要があります。また「空気圧縮時に発生する温度上昇」を利用して適切なタイミングで自然着火させるのがディーゼルエンジンです。
ホンダのS07B型エンジンに使われている技術で、17年デビューのN-BOXから搭載されているとのこと。
なぜノッキングが起きにくくできるのか?
答えは「バルブに熱が伝わりにくくなる」からだそうです。
ノッキングの起きる要因は上記POINTでも解説し通りですが、バルブに熱が籠ってしまい、その高温になったバルブがきっかけで「着火→ノッキング」になることもあるようです。
イメージしやすいのは、赤くなるほど熱した鉄でタバコに火が付いてしまう感じでしょうか。
本題に戻しますと、
従来のバルブは燃焼室側の中央が窪んでいる形状(カブのバルブ)でフラットな部分にも小さな凹凸がありますが、画像のバルブは面全体がフラットになっており鏡面になっております。
- 従来のバルブ:窪みや小さな凹凸のせいで、熱に晒される面積が大きい
- 鏡面のバルブ:フラットで鏡面になるほど平らなので熱に晒される面積が小さい
という事
そもそも、バルブに熱を溜めないようにしようといった技術でした。
そう考えると圧縮率が上がり、ハイオク推奨が殆どのボアアップには相性がいいのかもしれませんね。
筆者の場合、鏡面にしただけで完全なフラットにはしていないので効果薄だと思いますけど・・・
結果ただの自己満ですね。(笑)
バルブの擦り合わせ


擦り合わせも行っておきましょう。
後で知ったことですが、バルブの当たり面は細い方がパワーが出るようですね。ただ、髪の毛のように細いと一瞬のパワーを手に入れる代わりに、力が一点集中するためバルブシールの寿命が短くなる傾向にあるようです。
ちなみにカブの吸排気のバルブの当たり面は1㎜~1.5㎜の間に収まっていればOK。
測ってはいませんが、共用範囲には収まっていそうです。
擦り合わせ方法

方法は単純で、タコ棒バルブを貼り付けバルブコンパウンドを当たり面に中目、細目の順に「叩き回し」ながら、言葉通り擦り合わせていきます。
どのくらいまでやればいいのか?
いくつかのサイトを拝見しましたが「適度にすり合わせを行う」等、表現が曖昧で明確な答えがなかなか見つかりませんでした。中には45秒程度などと時間で書かれている物もありましたが「秒数で作業しても、キッチリ当たりが出なかったら意味ないやん!」と腑に落ちませんでした。
そこで筆者なりに考えた結果
- スタンプしたとき光明丹が1週付着すること
- スタンプの幅が許容範囲内であること(カブ:1㎜~1.5㎜)
1.のスタンプについては
- バルブフェースに光明丹を塗ってスタンプし、バルブシールを確認
- バルブシールに光明丹を塗って、バルブフェースを確認
の2方向からの確認としました。
答えは分かりませんが「バルブ擦り合わせ」の要点は抑えているのではないかと思います。
ちなみに光明丹ですが、印鑑のインクで代用できます。また、塗る時は綿棒を使うと塗りやすいです。
応用として、インクを塗ったカバー類をパッキン紙にスタンプすれば、ガスケットも自作できちゃいます。
シリンダーヘッドの組付け
すべての作業が終わったら、いよいよ組付けて完成です。
ここまで16時間程度、完成まで2日半に分けて作業しています。長い時間ですが集中しすぎてゾーンに入っていたようで、1日が一瞬でした。
細かい作業は省きますが、パーツリストを確認しつつ取り付けていきます。
カムのギヤにある印とフライホイールのTがケースの切り欠きに合うように取り付けることを忘れずに!
そのあと、フライホイールを手で回しスムーズに回るか確認しましょう。違和感がある場合は最初から見直してください。
最後にタペットのクリアランス調整をして完了です。
ヘッドに使う部品
モンキー系の横型エンジンは互換性がありますが、ヘッドガスケットは排気量により別途購入が必要です。
タペットのクリアランス調整
カブ90(HA02)の調整幅は
吸気側・排気側共に0.05mm(±0.02)が規定値
つまり、シックネスゲージの0.05㎜で調整を行い、0.07㎜が入らなければOKということ。
調整にはタペットアジャストレンチなる工具を購入しておきました。
やはり工具は偉大ですね!無くてもできる作業ですが、専用工具を使った方が断然やり易いです。
なお、この工具は「ロ型」と「I型」があるため自分のバイクに合ったものを選択する必要があります。
分からない方は両方入ったセットを選ぶようにしましょう。
エンジン始動!
待ちに待ったエンジン初始動です。
ワクワクとドキドキが相交じり勃・・・
頭がおかしくなりそうです!
いざ点火!
トトトトトトトトトッ
カブのジェントルな音が響きます!
ウェイウェイウェイ!!歓喜!もうイッ・・・
無事エンジンが掛かりました!
アクセルを開けるとエンジンからパンッ!・・・
!?
もう一度、アクセルを開けるとパンッ!・・・
あっためてもパンッ!
朝はパン、パンパパン♬・・・
意味がわかりません。
バックファイヤー?の症状に一気に萎えました。
ですが、実を言うと「なぜ!?」と同時に「やっぱり?」と思い当たる節がありました。
それはポート加工まで遡るのですが、実は加工時に一瞬だけ吸気側のバルブシールにビットを当てておりました。
ただ、バルブすり合わせで見えなくなるほど少しの傷だったので、ヤバイと思いながらも、入念にすり合わせを行い作業を進めていたのです。
タイミングが遅れ気味になると、バックファイヤーの症状が出るとの記述もあったので、タイミングチェーンのズレも再確認しましたが問題無しでした。
かろうじて、アクセルをゆーーっくり4分の1程度回す分にはバックファイヤーしなかったので、時間もないことから一旦作業を完了し1週間通勤に使いました。
次回の確認作業でもしもがあった時のために、ヘッドを購入したのは言うまでもありません。
追記
バックファイヤーと思っていた症状ですが、別の原因でした。
まとめ
今回は初めてポート加工というロマンの詰まった作業を行ったわけですが、初めての作業なので不安でしかありませんでした。
ですが、いざ始まってしまえば非常に楽しく、時間を忘れて作業してしまいました。
結果的にシールの傷が原因?でバックファイヤーするようになってしまったのですが、これも良い経験値です。
※バックファイヤーの原因が100%バルブシールの傷とは断定出来ていない状態です。
作業自体もスムーズにできたと思います。
確かに元々の知識も確かにありますが、色々な資料を読み漁り、構造や仕組みを理論建てて理解していたのがスムーズな作業に繋がったと思います。
ちなみにウェビックというサイトで無料でパーツリストを確認できますので活用してください。
下記のような、指南書を読んでからスタートするのもおすすめです。
初心者の方でも構造さえしっかり理解すれば腰上ぐらい、すぐ分解組み立ては出来てしまうと思いますよ!
ボルトを外してバネが飛び出してくるのは「タイミングチェーン・テンショナー」ぐらいだと思いますので安心してください。
タイミングチェーン・テンショナーですらシリンダー&ピストン交換では外さなくても作業できます。
自分にはできないと不安になる気持ちも理解できますが、出来るようになるとメッチャ楽しくなりますので、是非殻を破って、挑戦してみてください。
ではまた!